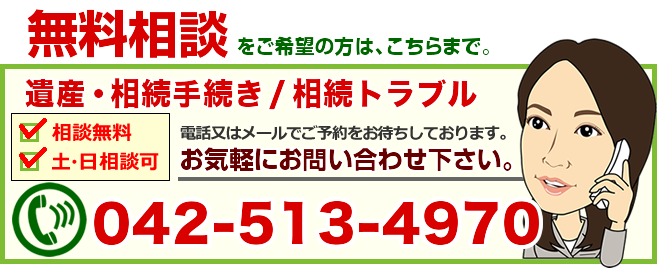未成年者がいる場合に必要となる手続き
父、母、子2人(未成年者)の4人の家庭で、父が亡くなった場合、遺産分割協議はどのように行われるでしょうか。
通常、未成年者の法律行為は、親権者である父母が代理します。
ですが、亡お父様の相続について相続人間で遺産分割協議をしようとした場合、親権者であるお母様も相続人となりますので、お母様がお子様を代理して遺産分割協議ができるとしてしまうと、実質お母様が一人で協議することになってしまい、お母様がお子様の利益を無視して、自分だけに有利な協議をすることもできることになってしまいます。
このように、未成年者と親権者(両親)との間で契約等の法律行為をする際、両者の利益が相反する場合は、未成年者の利益を守るために、家庭裁判所で未成年者のために特別代理人を選任してもらい、特別代理人が未成年者を代理して遺産分割協議を成立させる必要があります。
上記の例では、未成年者である2人の子について、それぞれ特別代理人を選任してもらい、お母様と特別代理人2名の合計3名で遺産分割協議を行います。
概要
| 申立する裁判所(管轄裁判所) | 未成年者の方の住所地を管轄する家庭裁判所 |
|---|---|
| 申立人 |
|
| 申立費用(実費) |
|
| 必要書類など |
|
手続きの流れ
- 申立から選任審判までに要する期間は概ね1ヶ月前後です。
- 準備期間は事案により異なりますので、ご相談ください。


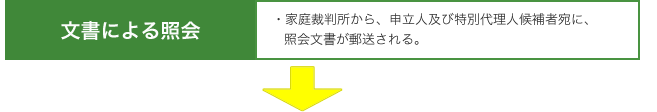
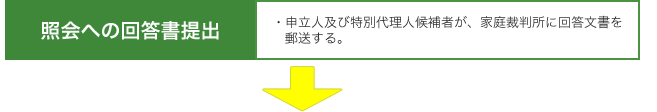
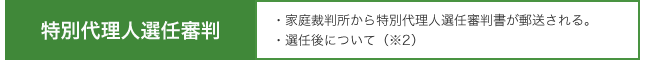
実務的には、申立人である親権者が特別代理人候補者を家庭裁判所に推薦し、問題なければ、その候補者が選任されています。
特別代理人は、親権者の親族等ではなく第三者の方が望ましいですが、親権者の親族であっても未成年者の保護が図られていれば選任されているのが実務の運用です。遺産分割協議のケースであれば、未成年者に法定相続分以上の相続財産が確保されているかがポイントになります。
※2.特別代理人に選任された後
特別代理人は、家庭裁判所で選任されてから職務として未成年者を代理することになりますが、実務的には、特別代理人選任の申立前に、特別代理人候補者の段階で、他の相続人との間で遺産分割協議の下打ち合わせを行い、遺産分割協議書案を家庭裁判所に提出して選任してもらう形になります。これは家庭裁判所が未成年者の保護が確保されていることを確認するための運用だと思われます。